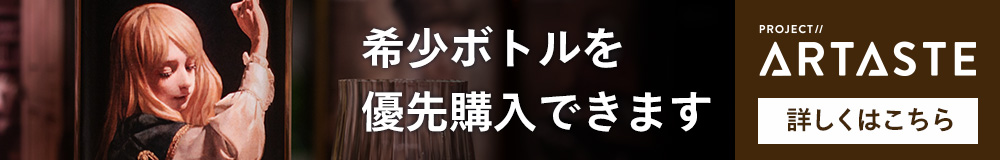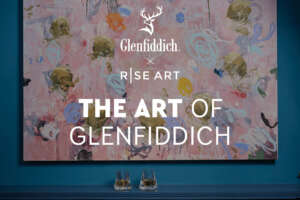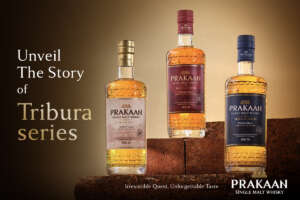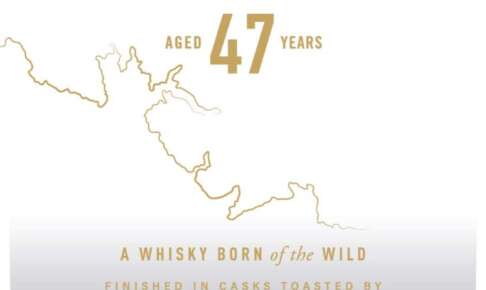長野県の小諸蒸溜所が地域交通を主導したニュースに続き、山形県の遊佐(ゆざ)蒸溜所が位置する遊佐町でも、ウイスキーを核とした地域振興の動きが加速しています。
遊佐町は2025年10月末、ウイスキーの魅力を最大限に活用した観光活性化事業、その名も「YUZA WHISKY TOWN(遊佐ウイスキー・タウン)」構想を発表しました。これは、単に蒸溜所を見学するだけでなく、地域全体を巻き込んだ「ウイスキーツーリズム」を推進するものです。
湧水の里に生まれた「世界が憧れるウイスキー」

遊佐蒸溜所の概要
遊佐蒸溜所は、山形県の日本酒メーカー9社が出資する焼酎メーカー、株式会社金龍を母体として、2018年11月に操業を開始した山形県初の本格ウイスキー蒸溜所です。
立地: 山形県飽海郡遊佐町。名峰・鳥海山の麓に位置し、「水の郷百選」にも選ばれるほどの豊かな伏流水(硬度46度の軟水)に恵まれています。
コンセプト: 「TLAS(トラス)」— Tiny(ちいさな)、Lovely(かわいい)、Authentic(本物の)、Supreme(最高の)— を掲げ、小規模ながら最高品質を目指しています。
酒質: フルーティーで華やか、透明感のあるクリーンな味わいが特徴。
評価: 2022年に初のシングルモルト「YUZA First edition 2022」をリリースして以降、ISC(インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ)などで3年連続金賞を受賞するなど、国際的にも高い評価を得ています。
ツーリズムへの慎重な姿勢からの転換

遊佐蒸溜所は操業当初、製造に集中するため、一般の見学を「当面予定していない」としてきました。しかし、ウイスキーが国際的な評価を得て、ブランドとしての注目度が高まる中で、地域貢献への期待も高まりました。
今回発表された「YUZA WHISKY TOWN」構想は、この慎重な姿勢から、地域全体を巻き込んだオープンな観光へと大きく舵を切ることを示しています。
「ウイスキーの町」としてのツーリズム構想
二つの蒸溜所を巡る体験
遊佐町のウイスキーツーリズムの大きな強みは、遊佐蒸溜所の他に、2023年操業の「月光川(がっこうがわ)蒸留所」という二つの蒸溜所が町内にある点です。

この構想では、通常は非公開エリアも含む両蒸溜所を巡るオリジナルツアーを核とし、参加者は「作り手の想いをじかに感じる」深い体験が提供されます。
食と文化との融合
ツアーでは蒸溜所見学だけでなく、ウイスキーに合うよう地元食材を活かした料理の試食会なども組み込まれる予定です。
参加者はウイスキーを「飲む」だけでなく、遊佐町の「食文化」や「風土」と結びつけて体験できます。
地域資源の活用: 鳥海山の伏流水、庄内地方独特の寒暖差など、ウイスキー生産に適した環境は、そのまま地域の魅力となります。
「水の良さ」の再認識: 町長は、「(ツーリズムを通じて)遊佐町民には、自分たちが飲んでいる水はこれだけおいしいものだということを日々感じてほしい」と語っており、地域住民のシビックプライド(郷土愛)の醸成にも貢献することが期待されています。
日本ウイスキー産業のツーリズムの深化

小諸蒸溜所の事例と同様に、遊佐町の動きも、日本のウイスキー産業における「ツーリズムの深化」という大きな流れを反映しています。
1. 二次交通・アクセス問題の解決
小諸では蒸溜所が周遊バスを主導することで、駅から離れた施設へのアクセスと地域周遊を同時に解決しようとしました。
https://www.barrel365.com/n2511081/
遊佐町の場合、観光客の駅からの二次交通(タクシーやバス)が十分ではないという課題があり、今回のツアー構想は、交通手段そのものを「ウイスキー体験」の一部としてパッケージ化することで解決を図ろうとしています。
地域と連携し、「点」から「線」、そして「面」へと観光客の流れを広げようとする視点は共通しています。
2. 地域全体での付加価値の創出
日本の新興ウイスキー蒸溜所の多くは、地方の美しい自然の中に立地しています。しかし、周辺に宿泊施設や飲食・観光施設が少ない場合も少なくありません。
観光客の囲い込みではなく、解放: 遊佐町と蒸溜所は、ウイスキーという強力なコンテンツを「町の顔」として活用し、その集客力を町全体に波及させることを目指す。
ウイスキーは時間をかけて熟成される商品であり、地域ツーリズムもまた、一過性のブームではなく、その土地の文化や風土を深く理解し、何度も訪れたいと思わせる「町のファン」を増やすことを目的とする。
遊佐町の「YUZA WHISKY TOWN」は、小規模ながら世界的な評価を得たウイスキーを旗印に、地域資源(水、食、景色、人の思い)を組み合わせることで、「蒸溜所単体では完結しない」、豊かな旅の体験を提供しようとしています。
こういった動きはこれからの日本のクラフトウイスキーが地域と共存していく上での、一つの成功モデルとなり得るかもしれません。
オリジナルツアーは、来年以降、日程と人数を限定して申し込みを受け付ける予定だそうです。